いつもの。
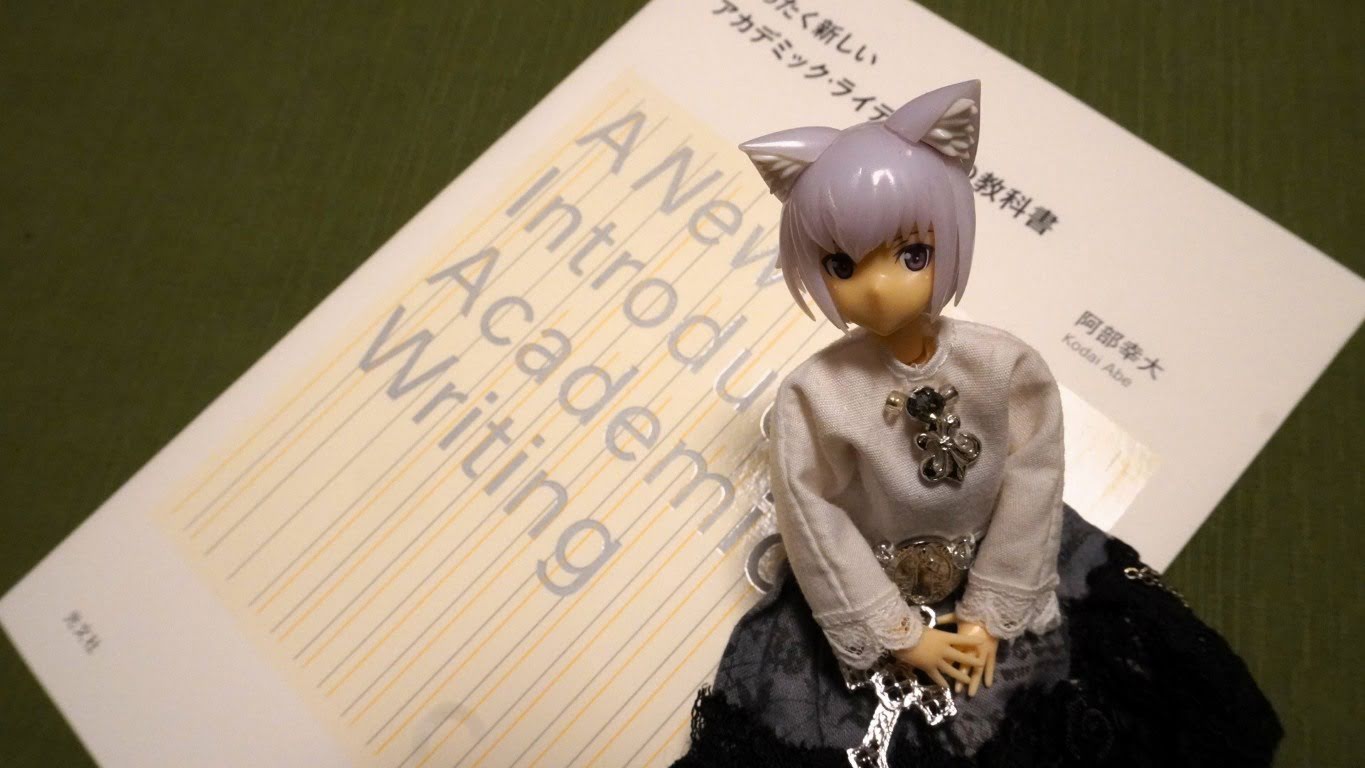
まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書
![]() まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書阿部幸大(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4334103804
まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書阿部幸大(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4334103804
人文学における論文はどういった文章であるか、そして論文を書くためにどのように文章を構成していけばいいか。良書。
論文の核となる主張(アーギュメント)を提示し、その主張が正しいことを論証するための本文をどう構築していけば説得力が生まれるのかが書かれている。
パラグラフになるかという観点でトピックを選定する。「観察」と「解釈」の次元を意識するとどの記述が手薄なのかがわかる。ファクトについての周辺的な情報を盛り込みパラグラフを長くする。などが特に使えそうだと感じた。
製本家とつくる紙文具
![]() 製本家とつくる紙文具: オリジナル文具づくりから文庫本の仕立て直しまで、35のアイデア永岡綾(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4766139852
製本家とつくる紙文具: オリジナル文具づくりから文庫本の仕立て直しまで、35のアイデア永岡綾(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4766139852
紙製の文房具の作例とつくり方。紙の雑貨がどうつくられているのかやその技法を知れる本。
自作ノートパッドやストレージボックス、文庫本の改装などなど。
巻末にある紙文具づくりの道具一覧や糊の種類と使い方、箔押し文字の入れ方は特に面白く感じた。
仕舞う: 美しい収納の知恵
![]() 仕舞う: 美しい収納の知恵 (らんぷの本)小泉和子(編集) .https://www.amazon.co.jp/dp/4309757588
仕舞う: 美しい収納の知恵 (らんぷの本)小泉和子(編集) .https://www.amazon.co.jp/dp/4309757588
旧家においての家財調査で発見された機能的な仕舞い方について。
昔の生活における仕舞い方について書かれており、対象としては飲食器、家具調度品、衣類や古文書など多岐にわたる。 食器が割れないように和紙や絹で包む。掛け軸は羽根ぼうきでほこりを払った後、掛けたまま風帯の下まで巻いてから紐を外す。文書は紙縒りでくくる、行李にいれるなどなど。
保存するための伝統の知恵。知らないものが多く興味深く読んだ。
図書館を学問する
![]() 図書館を学問する: なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか佐藤翔(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4787200887
図書館を学問する: なぜ図書館の本棚はいっぱいにならないのか佐藤翔(著) .https://www.amazon.co.jp/dp/4787200887
図書館情報学を専門にする著者が図書館を対象に行った研究を紹介する本。
図書館が年間どのくらい本を導入して破棄しているのか、書架番号の大きさと利用者の行動をVRで比較した研究、図書館利用者のクラスタリングなどなど。
こういう研究が図書館をめぐっておこなわれているのかと、研究の様子を知れる本。